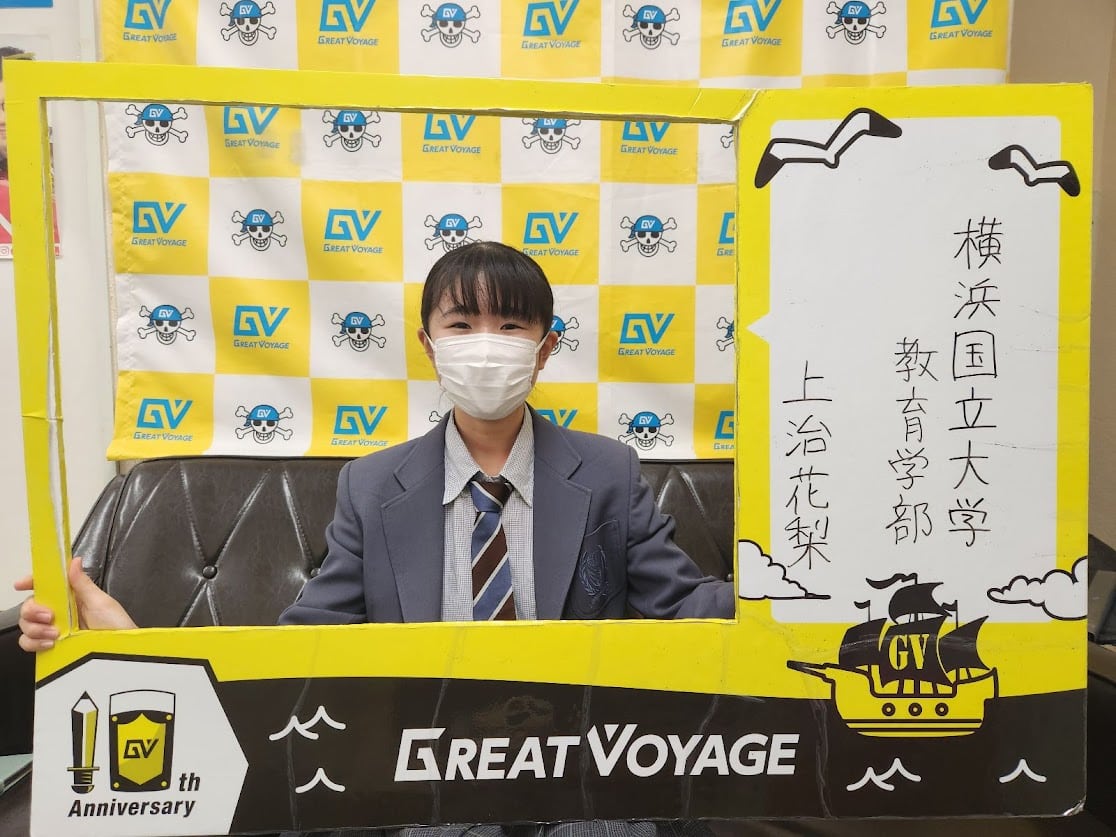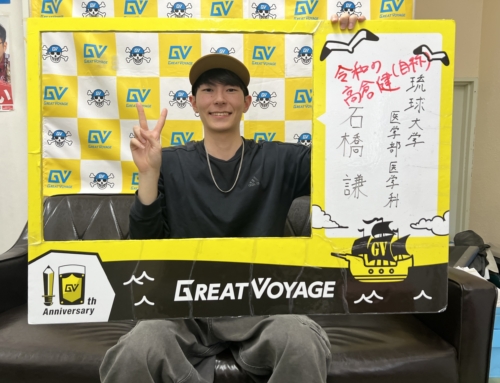目次
Q.合格の瞬間を振り返って
横浜国立大学の合格発表の日、自分の番号を見つけた瞬間、「本当に私が受かったの?」と信じられない気持ちでいっぱいでした。面接では暗記した自己PR以外はアドリブで乗り切り、小論文も600字を一段落で書いてしまうという失敗をして、「これは落ちたな」と思っていました。試験が終わった直後には「これで受かったら、この大学を疑っちゃうわ。横国に限って、こんな人を選ぶはずがない。私なら絶対選ばないな」とまで思っていたので、合格を全く信じていませんでした。
結果を見たときも、「間違いじゃないの?」と何度も確認しました。家族に合格を報告すると、「焼肉に行こう!」と言われて、そこで初めて「あっ、焼肉が嬉しい。あ、そっか、合格したんだ」と少しずつ実感が湧いてきました。その後、入学料の振り込みや手続きなどが進む中で、ようやく「これから本当にこの大学で学ぶんだ」という気持ちを受け入れ、現実として実感できるようになりました。
Q.小論文対策で意識したこと
小論文試験では、事前の対策が確実に役立ちました。特に、自分の中にいる「イマジナリ田名さん」という批判的な視点が大きな助けになりました。この「田名さん」は、自分が書こうとした内容や構成に対して、「それじゃダメだ」「根拠は?」と厳しい指摘を投げかけてくる存在です。試験中も、文章を書き進めながら「田名さん」とのやり取りを繰り返し、提案を受け入れつつも自分なりの修正を加えながら文章を作り上げました。
例えば、書いた内容に対して「その根拠は何?」と質問されることを想定し、言い訳や補足を頭の中でまとめ、それを文章に落とし込む作業を続けました。このプロセスにより、自分の主張をより論理的に支える形にできたと思います。
この批判的思考力は、まさに普段の練習から得たものです。「イマジナリ田名さん」という存在は、自分を客観的に見つめ直し、必要な修正を加えるための象徴的なツールでした。試験の緊張感の中でも、この思考プロセスがあったおかげで、90分間押しつぶされることなく取り組むことができたと感じています。
Q.面接でのエピソードと成長
面接について、最初は全く自信がありませんでした。練習の時も全然答えられず、最終的には暗記に頼ることを選びました。20問ほどの質問を想定し、それに対する答えを準備しましたが、実際に暗記できたのは志望理由と自己PRの2つだけでした。それ以外は、その場で自分が考えてきたボランティアの経験やキーワードをもとに、即興で答える形になりました。ただ、暗記を試みたおかげで、必要な語彙や具体的な要素は自分の中に残っていて、面接で瞬時に引き出すことができました。この点は練習の成果を感じた部分です。
面接に向けた大きな転機は、校長先生との面接練習でした。学校側が設けてくれたこの機会では、「準備した答えが覚えられていない」という状況に直面しました。そこで、「等身大の自分で臨もう」と切り替えて挑むことにしました。結果的に、その決断が功を奏し、緊張感や自分を縛り付けていたプレッシャーが消え、「人間ってこんなに喋れるんだ」と感じるほど自然に話せました。
この経験を通じて、他の人とも練習を重ねることの重要性に気付きました。特に、初めて会う人との練習では、自分に対する固定観念や緊張が少ないため、よりリラックスして話せることが分かりました。この気付きから、他の人とも積極的に面接練習を試すようになり、次第に自信を持って臨めるようになりました。
Q.GVに入塾した理由とは?
GVに入塾したのは、自然な流れでした。もともと中学が一緒だったユイカ先輩やキワ先輩から、「この塾で志望校に合格した」と聞いたことがきっかけの一つです。また、母もGVの合格体験記を読んでいて、「ここ良さそうじゃない?」と勧めてくれたことが、背中を押してくれました。
GVの合格体験記を読んでいるうちに、先生たちの個性や指導スタイルが見えてきました。どの生徒も「先生に気軽に相談できた」「親身になって指導してくれた」と書いていて、それが一貫しているので「これは本当なんだな」と感じられました。特に、誰かに言わされているような言葉ではなく、生徒自身が感じたことがそのまま伝わってきたので、信頼できる塾だと思いました。さらに、生徒と先生の距離が近く、親切で聞きやすい雰囲気があるのも魅力的でした。GVでは、他の塾では追加料金がかかることが多い個別指導が、「料金を気にせず気軽に組める」とたくさんの人の合格体験記に書かれていて、「こんなに手厚いサポートがあるんだ」と驚きました。
他の塾も一応見比べてみましたが、どれも「お金を払って教えてもらう」形式的な印象が強く、自分がしっくりくるとは感じられませんでした。一方で、GVは生徒へのサポートが手厚く、先生との距離が近いオープンな雰囲気があり、「ここなら安心して頑張れる」と思えたのが決め手でした。
Q.大岩先生の指導で得たもの
大岩先生には、小論文について相談をしたり、意見を求めたりする場面でお世話になりました。とにかくスピード感があり、話題がどんどん進むため、ついていくのが難しいと感じることが多かったです。質問を考える時間もほとんどなく、圧倒されることもしばしばでした。しかし、そのテンポの速さが自分を鍛え、自分の語彙力や考え方を広げてくれました。大岩先生とのやりとりが、小論文を書く際の選択肢が増やし、社会問題をより深く考えるきっかけを与えてくれたと感じています。
特に印象的だったのは、大岩先生が現代の社会問題について、自分ごととして捉えさせるような視点を与えてくれたことです。授業を受ける前は、朝のニュースをなんとなく流し見しているだけでしたが、授業後には「このニュースは本当に正しいのか?」「別の視点ではどう報道されているのか?」といった批判的な視点でニュースを考えるようになりました。また、同じニュースを複数の情報源で比較するなど、情報の裏にある構造や意図を意識するようになりました。これにより、物事を多面的に捉える力が養われたと感じています。
さらに、大岩先生の授業では、一見関係のない事柄を独自の視点で結びつけて話されることが多く、その話を聞きながら自分なりに「繋がるポイント」を見つけ出す作業がとても刺激的でした。受験という枠を超えて、今後の人生に役立つ多くのものを得ることができたと思います。
Q.與那城先生が教えてくれた英語の考え方
與那城先生は、ただ英語を教えるだけではなく、英語の「解き方」や「考え方」を教えてくれる先生でした。英語を学ぶ上で、「覚えることが重要」と考えがちですが、それだけではなく、自分の身の丈に合った方法で取り組むことの大切さを教えてくれました。特に英作文では、「難しい表現を無理に使うよりも、自分に合った英語で書こう」と指導してくれたことが印象的です。
授業では、「新しい表現を覚えたからといって、すぐに使おうとして間違えるのはカッコ悪い」と冗談交じりに伝えながら、生徒が自然体で取り組める雰囲気を作ってくれました。例えば、「切磋琢磨」という日本語を英語で表現しようとして悩んだとき、拙い表現を書いてしまっても、笑いながらも「この表現も悪くない」と褒めてくれたり、別の表現方法を教えてくれたりしました。その一方で、学んだことを覚えていなかったり、適当に答えたりすると容赦なく笑われることもありましたが、努力して覚えたことには必ず正当に評価してくれる先生でした。
英作文に対する取り組み方や、表現の幅を広げる方法を教えてもらいながら、英語への苦手意識も少しずつ変わっていきました。それまでは英語が「大嫌い」でしたが、與那城先生の指導を受けて、「嫌いだけど頑張ってみようかな」と思えるようになりました。先生の厳しさと優しさが混じった指導のおかげで、少しずつですが英語に対する意識が前向きに変わったと感じています。
Q.塾での経験を通じて成長したこと
GVでの学びを通じて、以前は「こんなことを聞きたいけど、そこまで深く聞きたいわけじゃない」とか、「軽い質問をしてしまったら、もっと重大なことを聞きたい人の邪魔になるのでは」といったことを考えすぎて、質問するのをためらう部分がありました。しかし、GVでは「気軽に聞いていいよ」という雰囲気が自然と作られていて、その環境のおかげで、少しずつ遠慮せずに質問やお願いができるようになりました。
最初はマネジメントの方々にも「こんなことをお願いしていいのかな」と遠慮がありましたが、次第に「これをお願いします」と具体的に頼むことができるようになり、自分の要望をしっかりと伝えられる力が身につきました。
学力の向上はもちろんのこと、特に自分の中で大きな成長を感じたのは、コミュニケーション力が高まったことです。相手に気軽に聞いたり、自分の意見をしっかり伝えたりするスキルが身についたのは、GVのオープンな雰囲気とサポートのおかげだと感じています。
Q.後輩たちへメッセージ
高校2年生の終わり頃から、自分の進路や興味について少しずつ考え始めることが重要だと思います。特に、「自分が何をしたいのか」という核となるものを見つけることが大切です。自分が4年間続けられるものは何かを考え、その核を見つけることで、学部や志望校といった具体的な進路が決めやすくなります。早めにいろいろと決めておくことは本当に大事で、これがその後の進路選択をスムーズにする鍵だと思います。
2年生の段階では、進路がまだ定まらない人も多いですが、それでもいろいろなことに興味を持ち、ふんわりと方向性を考え始めるだけでも十分です。3年生になる頃には、自分のやりたいことを少しずつ絞り込み、夏頃までには志望校や学部の方向性を固められると理想的です。特に、学部選びは「自分はこれがしたい」という事が重要で、この大枠を決めておくことで、進路全体が見通しやすくなります。
日頃の学びを楽しむ
日頃の学びを楽しむ姿勢も大切です。授業で振り返りを書く時間を設けられることがあると思いますが、この時間は非常に重要です。自分の考えや経験を正直に書き出すことで、学びが深まると感じました。例えば、日常の出来事や自分の体験を学びと結びつけると、振り返りが単なる作業ではなく、自分自身の理解を深める時間になります。このように、勉強に関わる一つ一つの事を「やらなきゃいけないこと」としてではなく、自分が選んでいるものとして楽しむ意識を持つことで、学習がより充実したものになると思います。
塾の活用方法
塾では、授業が被らないように組まれており、計画的に取り組みやすい環境が整っています。参加したい人が参加できる個別や少人数のゼミなどでは、他人の話を聞いたり意見を交換したりすることで、新たな視点を得られることも多いです。
自習室にこもって頑張るのも楽しいと思いますが、それだけでなく、先生や他の生徒との交流を通じて学びを広げることもおすすめです。特に、S教室のような開放的な環境では、集中しながらも他校の生徒や先生との会話を楽しむことができ、自分の視野を広げる良い機会になります。また、授業や演習などの提供されている機会を積極的に活用することも重要です。自分だけでやろうとすると限界がありますが、他人と関わることで学びの幅が広がります。
入塾当初、私は自分一人で塞ぎ込んでしまうこともありましたが、その反省を活かして、最初から積極的に質問したり、他の人と交流したりすることが成長につながると実感しました。学校とは違う塾の特性を活かし、新しい環境での学びを楽しんでほしいと思います。「自分から動くこと」を意識し、塾での時間を有意義に過ごして欲しいです。